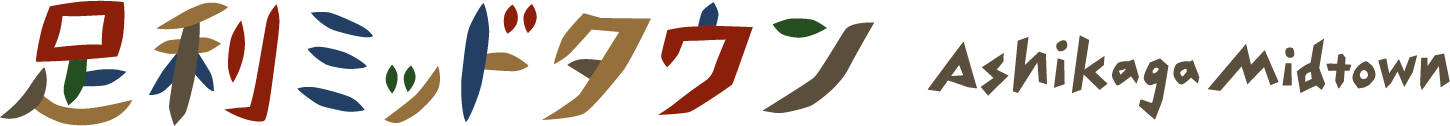【このまちを知りたい旅Vol.1 株式会社マルキョー(Cfa Backyard Winery)】

このまちでお店を開いて、
店や仲間を通して色々な繋がりができた。
けれどまだまだこのまちのこと、知らない場所も人も沢山ある。
「足利をもっと知りたい!」の想いに導かれて、仲間と時々ローカルツアーをしてみることに。
春、植物たちが一気に芽吹きだしたある日。
足利の南に位置する島田町の工場を訪ねた。
『株式会社マルキョー』。
今年で創業70年となる今や北関東唯一のラムネ製造会社である。


「主力商品であるラムネやかき氷のシロップは、夏祭りの時期には、地域の自治会から直接発注がくるんです」。
長年地元の人に愛される自社商品のことを、誇らしげに話すのは、3代目の春香さん。
自慢のシロップを炭酸で割ったウェルカムドリンクは、色鮮やかにきらめいて、なんだかお洒落なカクテルのようだ。

栃木土産の定番となったご当地ドリンク『レモン牛乳』の原料であるレモンシロップも、かつてはマルキョーで作っていた時期があるというから驚いた。
太平洋戦争終結後の、まだ物がない時代に設立された同社で、最初に製造された商品は、大豆以外の原料で作られる「醤油の代用品」だった。
戦後しばらく続いた配給用物資として、当時東北まで流通したという。
その後、ジュース、シロップの製造を始める。
紙コップ用のジュース販売機も製造し、ジュースとセットで各地の商店の店先に設置。
創業者である春香さんのお祖父さんが撮影した、ジュース販売機に群がる当時の子供たちの写真を見せてもらった。販売機の上にジュースのタンクが付けられているスタイル。
その時、美川のしょーちゃんがポツンと「いぶきビルの1階にジュースの販売機あったって親父が言ってたような、ジュースの噴水みたいな感じの」。
「それそれ!」と春香さん和香さん姉妹。
いぶきビルとは、現在区画整理の用地となっている、みずほ銀行斜め向かいの更地にあった。デパート高島屋やケンタッキーが入った時代もある、足利のランドマーク。
1970年代にラムネ製造を開始、後に空前のラムネブームが到来し、100万本売れた年も。
「ラムネは黒船に乗ってやってきたんですって」。
『レモネード』が訛って『ラムネ』になったという説がある。
柑橘飲料はビタミン補給用に船旅で重宝された。

戦時中の日本では、戦艦大和にラムネの製造機がのっていたそうだ。
現在マルキョーで使用しているラムネ製造機は、当時戦艦の乗組員だった大阪の方が作ったもの。
2代目の敬公さんは根っからのワイン狂。農大卒業後、国税庁試験所を経て、山梨県のワイナリーに勤務。その後、家業マルキョーに勤務しながら、ラムネやシロップの閑散期である秋冬は、ワインメーキング・コンサルタントととして飛び回り、全国各地のワイナリーの立ち上げに参画する。
春香さんも農大卒業後、父に同行しワインメーカーとしての経験を積み、ワイン醸造技術管理師の資格を取得。そして2012年ついに、自社内に「Cfa Backyard Winery」を設立した。
数種類試飲をした後、醸造タンクを見せてもらうことに。
工場の一角に置かれた乳白色のタンク、中には淡い黄金色の白ワインがたっぷり。
「この中に入っているワイン、うちの畑で採れたぶどうで醸造した初めての商品なんです」。

足利で実ったぶどうを使って足利で醸造したワインを味わってもらいたい、その想いを胸に、ワイナリーから車で3分ほどのところに自社畑を借りて、124本のぶどうの苗を植えた。
元はトマト畑だった土地。雨を媒介にする病気から守る為、ビニールハウスの中で育てている。
「消毒も少なくて済むし、水も4分の1の量で済むんだよ」と敬公さん。
綿密な計算と経験が詰まった畑。御厨用水からひいた水を点滴のように絶え間なくポタポタと散布する。地面には市内で肉牛の肥育をしている長谷川農場のたい肥が撒かれ、所々にからし菜が花をつけている。からし菜はぶどうの病気を防ぐ作用があるそう。
「これ今しか見られないぶどうの涙」。
和香さんが教えてくれたのは、剪定した枝先から滲み出る透明な樹液、通称「ぶどうの涙」。
肌に良いというので作業しながら顔にペタペタ塗っているという。
生き物を育てていると、季節それぞれ楽しみがあるものだ。

ワインショップ和泉屋のけんちゃんは、ずっとこちらのワインを扱ってきたけれど畑に来たのは「初めてなんだよ」と、辺りを見回しながらほーっと息をひとつついた。
2021年6月、Cfa Backyard Wineryはついに、自社初の足利産ワインをリリースする。
気になってはいたけれど足を踏み入れるきっかけが無かった。
まちの小売店で眼にしているし飲んだこともあるけれど、このワインに作り手のどんな想いが込められているのかどんな家族の物語があるのか知る由も無かった。
今回、ワインショップ和泉屋けんちゃんが繋いでくれたこの縁。
いつの時代も、商品への深い愛情を持ち続けてきた作り手の熱いハートに共感しました。
また新たな縁を手繰って【このまちを知りたい旅】に出るとしよう。